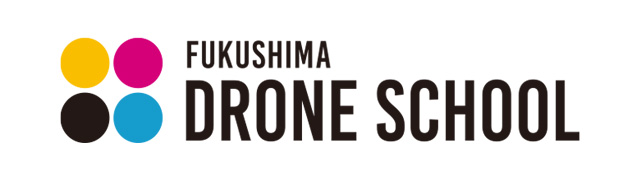はじめまして!ドローン事業部マネージャーのOHTANIです。
当社では、空から水中までドローンに関わるさまざまな事業を展開しています。
そのなかで得た最新の情報や気づきを、ブログを通じて発信していきたいと思います。
初投稿となる今回は、2025年に改正された空のドローンに関わる規制について紹介します。
目次
- はじめに
- ドローンは資格が必要?制度の背景
- 2025年ドローン規制改正のポイント
- 各業界への影響
- 建設・測量分野
- 農業分野
- 物流分野
- 企業が今から準備できること
- まとめ
(この記事の対象)企業でドローンを導入している方、導入を検討している方
はじめに
ドローン(無人航空機)は、建設・農業・物流・インフラ点検などさまざまな分野で活用が拡大しています。これを受けて、国土交通省や経済産業省などは安全運用に向けた法規制を整備し続けています。特に2022年以降、重量100g以上の機体登録や操縦者資格の制度化が進みました。2025年はさらなる改正が予定されており、申請手続きの簡素化や安全基準の強化が行われます。ここでは、最新の制度改正の大切なポイントと業界別の影響、企業が取るべき対応策などをわかりやすく解説します。
ドローンは資格が必要? 制度の背景
ドローンを飛行させるには「航空法」に基づく手続きが必要です。たとえば、重量100g以上の機体は屋外飛行の際に「機体登録」や国土交通省への「飛行許可」手続きが基本的に必要となります。とくに、人が多く住んでいる場所(人口集中地区といいます)の上空での飛行や、日没後の夜間飛行、機体を直接目で見ず、機体カメラ映像をもとに操縦する目視外飛行など、リスクの高い操縦方法は「特定飛行」と呼ばれ、事前に国土交通大臣の許可・承認を取ることが義務付けられています。例えば農業での農薬散布は、「物件投下」と呼ばれる上空からモノを落とす危険な飛行(=特定飛行)に該当することから、散布前に許可申請が必要です。
近年の制度改正では、操縦者の国家資格(無人航空機操縦者技能証明)や機体の認証制度を導入し、一定条件下では許可が不要となる運用も始まりました。たとえば、総重量25kg未満のドローンで操縦者が技能証明を持ち、認証を取得している機体を操縦する場合、夜間や目視外飛行などでも個別の許可申請を省くことができます。一方で、25kg以上の大型機や物件投下、危険物輸送などは従来どおり厳格な許可が必要です。このように、認証取得による利便性向上と安全基準維持の両立が図られています。なおここでは詳しく触れませんが、国家資格がなくてもドローンを飛行させることは制度上可能です。
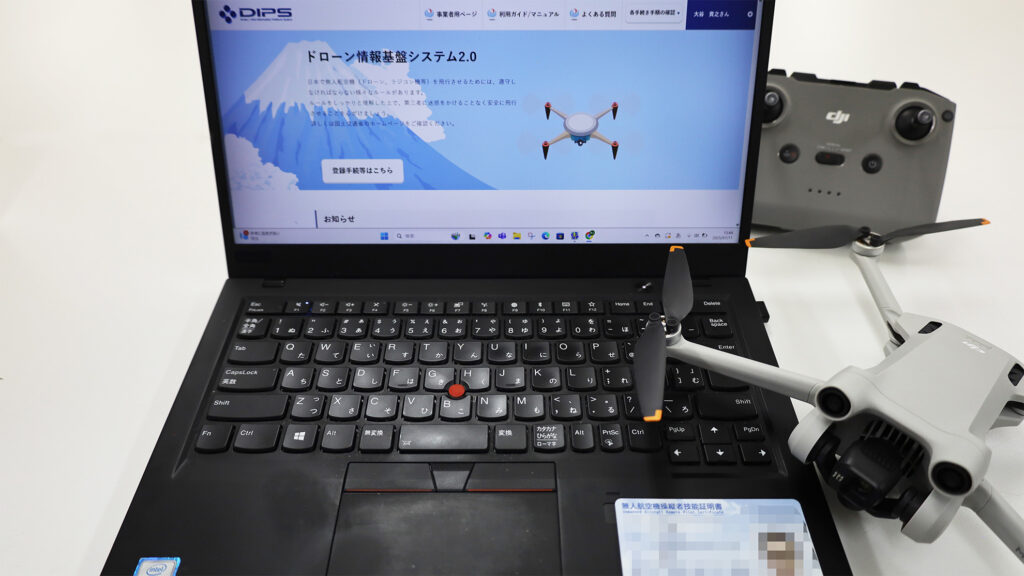
2025年ドローン規制 改正のポイント
ここからは2025年に実施または実施が予定されている制度改正についてご紹介します。
- 審査要領の改正・申請手続簡素化
国交省は2025年2月に「カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)」に関する審査要領を改正し、3月24日から施行しました。これにより、申請様式や添付書類が一新され、更新・変更申請の停止や申請処理の迅速化が行われました。オンライン申請ポータルも整備され、手続きが分かりやすく案内されるようになりました。 - 航空局標準マニュアルの改正
2025年3月31日付で「航空局標準マニュアル」が改正されました。この標準マニュアルはドローンを飛行させる際の手順を示すもので、自社の名称を記載することで飛行許可・承認申請の添付書類として使用することが可能です(自社オリジナルのマニュアルを作成することも可能)。このマニュアル改正に伴い、目視外飛行の細分化(補助者あり・なし)や風速5m/s以上、雨天時の飛行など、安全運航の注意事項が更新されました。
- 民間ライセンスの優遇廃止
2022年6月以降、ドローン操縦技能証明(JUIDAなどの民間ライセンス)から国家資格(無人航空機操縦者技能証明)への取得移行を促す動きが進められてきました。その結果、2025年12月5日以降、民間ライセンスによる飛行許可申請の簡略化措置が廃止されることになります。民間ライセンス自体は有効ですが、申請書類の省略や特典はなくなります。今後は国家資格の取得が実質的に必須となるため、企業は操縦者の国家資格取得を検討する必要があります。 - レベル3.5・4飛行の本格化
空港周辺以外の無人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル3.5)や、地域単位のレベル4飛行(カテゴリーIII)が現実味を帯びてきました。国交省は2025年3月からレベル3.5飛行に関するケーススタディを公開し、地域(エリア)単位のレベル4飛行の安全策例を福島・長崎モデルで示しました(引用:国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/koku/content/001881974.pdf)。これにより、災害時の物資輸送や離島サービスなど、新たな商用利用が見込まれています。
各業界への影響
こうした改正は企業にどのような影響があるのでしょうか。業界ごとに詳しく見ていきましょう。
建設・測量分野
広大な現場の測量・点検などにドローンが急速に浸透しています。従来は測量機器を持って人が現場を歩いていたため、範囲が広いほど時間とコストがかかりました。しかし、ドローンによる空撮測量なら上空から広範囲を短時間でデータ化でき、高低差のある危険箇所も安全に計測できます。解析・3D化ソフトで進捗管理も効率化し、工数削減が期待できます。点検作業でも、橋やビル外壁の高所点検では従来の足場組み立てが不要になり、作業員を危険にさらさず安全性が高まります。これらにより人手不足や事故リスクの解消、工期短縮が実現します。
2025年改正の影響としては、許可・承認手続きの迅速化で飛行計画が立てやすくなるほか、操縦者国家資格の活用で夜間・目視外飛行の領域が広がります。たとえば、建設現場での夜間測量や無人機での資材運搬実証のような試みも進んでおり、レベル3.5飛行の運用次第では危険区域での自動巡回など新サービスの可能性が高まります。ただし、人口集中地域や空港周辺では依然として許可・承認が必要で、事前計画や安全対策の整備は必須です。また、12月5日以降は民間ライセンスでの優遇措置が廃止されるため、早めに国家資格を取得して体制を整えておくことをお勧めします。
農業分野
農薬散布や作物観測にドローンを使う農家も増えています。農業用ドローンは、広い圃場を短時間で散布でき、作業負荷を劇的に軽減します。ただし前述の通り、農薬空中散布は物件投下にあたるため、散布前に国交省への飛行許可申請が必要です。 2025年の改正による直接の規制緩和は限定的ですが、重要なのは安全運航体制の強化です。『航空局標準マニュアル(空中散布)』が改訂されたことで、物件投下のための操縦練習があらたに追加されました。これに伴い、物件投下の前後の重量変化に対応するため、5回以上の物件投下の練習が必要となります。農薬散布を業務として行う場合は必ず「航空局標準マニュアル(空中散布)」を確認し、マニュアルに沿った運用を行うよう心掛けましょう。

物流分野
過疎地配送や緊急物資輸送でドローン活用が検討されています。日本でも2月に東京都港区がレインボーブリッジ上空でレベル3.5飛行による物資輸送実証を実施しました。芝浦からお台場まで1.8kmを飛行し、災害時に孤立する地域へ医療機材などを届けるシナリオです(引用:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000059475.html)。また企業ではドローン物流の研究開発が活発化しており、最大離陸重量25kg以上の大型機体の開発なども進められています。2025年改正後は、レベル3.5飛行の実績が増え、ルート自動飛行(ウェイポイント飛行)の実用性が高まるでしょう。
一方、人の上空を目視外で飛行させる本格的な物流には、厳しい審査基準をクリアした機体(第一種型式認証)と高い操縦技術と知識をもった一等無人航空機操縦士ライセンスの保有が必須となります。また、物流ビジネスでは上空を複数の機体が行き交う形となるため、衝突回避システムなどの技術的安全対策がますます重要となります。企業は配送における安全基準の整備や、関連法令の最新動向の把握を怠らないことが求められるでしょう。
企業が今から準備できること
最後に2025年の改正にあわせて、企業が取り組むべき準備をご紹介します。
- 機体登録と情報更新
ドローンを運用するには国交省認証のDIPS2.0で機体登録が必須です。既存の許可・承認をお持ちの場合でも、2025年3月24日以降は新様式での申請が必要となります。申請前に機体情報・操縦者情報の最新化を必ず行いましょう。 - 操縦者資格取得
2025年12月以降は民間ライセンスの優遇措置が廃止されるため、国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の取得が重要です。ドローンを頻繁に運用する場合は、スクール(登録講習機関)のスケジュールを確認し、早急に取得準備を進めましょう。 - 飛行計画・安全対策の整備
建設・測量・農業など各現場での飛行にあたり、最新の安全基準に適合させる必要があります。とくに特定飛行が必要な場合は、改正された標準化マニュアルをよく読み、マニュアルに従った運用を行ってください。 - 国家資格と機体認証
国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を最大限に活かすには、取得資格(一等・二等)に合わせた認証機体(一種・二種)を使用する必要があります。これまで認証機体が少なく、資格制度を活かしきれていませんでしたが、2025年5月にドローンメーカー世界最大手DJI社の「DJI Mini 4 Pro」が第二種型式認証を取得したことで、一気に活気づいています。こうした機体の導入検討や今後の機体認証の動きにも注意を払っておきましょう。
問い合わせ・連携先の確認
法改正や許可取得について不明点があれば、国交省の無人航空機ヘルプデスクや専門の行政書士に相談することをお勧めします。企業内にドローン統括部署を設けるか、外部業者との連携窓口を明確化することで、法令遵守と安全運航を両立できる体制を目指しましょう。

まとめ
2025年はドローンの法制度が一段と整備されます。申請様式の変更やマニュアル改定により手続きが簡素化される一方、民間資格の優遇廃止や飛行条件の明確化により安全確保の基準も高まります。企業のご担当者の皆様は改正内容を正しく理解し、機体・操縦者の登録更新や資格取得、飛行計画の見直しなどを順次行っておきましょう。
当社SNSに登録いただくと、最新動向やお得な情報をお知らせいたします。
そのほか、ドローンに関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。